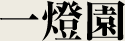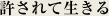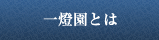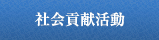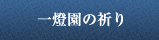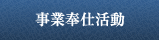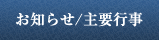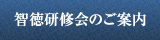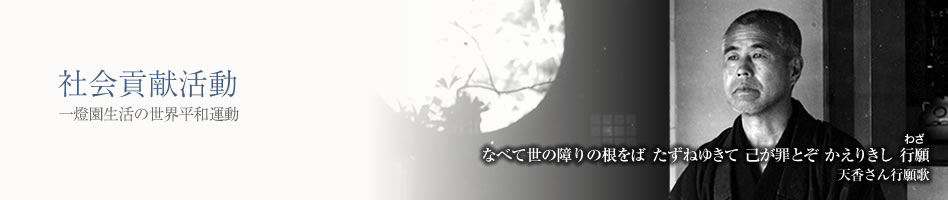- トップ
- 社会貢献活動(一燈園生活の世界平和運動)
一燈園生活の世界平和運動 —L.P.C運動(Life of Peace Creative movement)
一軒一軒、下坐の奉仕をつづけてゆく運動「六万行願」
1919(大正8)年、第一次世界大戦が終結し、国際平和機構として国際連盟が発足したとき、天香さんは、「上で国際連盟のような機関や条約をつくることも必要であろうが、真の平和は、一人ひとりの心の中に、争いの種をなくすることからはじめなければならない」と考えました。そして、同参を募り、バケツをかかえ、雑巾を手にして、一軒一軒、隣からまた向かいへと合掌しながら訪れ、下坐の奉仕をつづけてゆく運動をはじめられたのです。その運動を「六万行願」といいます。
世界平和への積極的な働きかけ「光卍十字運動」
真の平和はまず自分の心を正し、身を正し、生活を整えていくことから――と、あくまで内省的な六万行願に出発しつつ、外面的に進んで他の世界平和運動と手をとり合って進むべく、平和への積極的な働きかけとして、1930(昭和5)年、「光卍十字運動(ひかりまんじゅうじうんどう)」が発願されました。第二次大戦後には、一燈園は、日本国際連合協会やユネスコ運動、国際宗教同志会や世界宗教者平和会議(WCRP)の結成時より協力しています。さらに国際自由宗教連盟(IARF)にも参加し、一宗一派をこえ下坐の立場にたって世界平和の祈りに参与しています。
このようなことから外国からの来訪者も多く、つねに数名の滞在者があります。

国際宗教同志会席上にて
(写真中央が天香さん)
災害支援活動
1923(大正12)年の関東大地震に際し天香さんは、傷つき犠牲となった人たちに本当の慰藉(いしゃ)を届けようと、この未曾有の大災難を人間文明のおごりに対する天の戒めとして受けとめて懺悔するとともに、救援隊を一燈園から出動させ、傷ついた人々や焼け出された子どもたちの救護、食料の炊き出しなど、被災地の各地での救援活動に尽力しました。
以来、絶えることのない戦争や自然災害の犠牲者の悲惨に思いを馳せ、一燈園では折に触れて、被災地行願や被災者緊急支援募金活動等、さまざまな支援活動を呼びかけ実施してまいりました。また、イスラエル在住の光友の方々と連携して、ユダヤ人の子どもとアラブ人の子どもが一緒に学ぶ「ハンド・イン・ハンド(手をつなぐ)」共学共存運動を応援しています。

東日本大震災被災地でのお見舞い奉仕
一燈園生活のひろがりと継承
一燈園生活に共鳴して下さる方々である「光友」が全国にまたがって光友会が結成されています。そして、行願や托鉢会や講演会など、地道な活動を続けています。
また、学校法人燈影学園による教育活動や一燈園生活の体験する智徳研修会の開催など、社会に向けて幅広い活動を行っています。